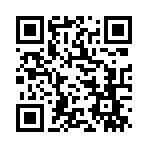› 木々と日々 › ふしぎ山 その2
› 木々と日々 › ふしぎ山 その22015年06月03日
ふしぎ山 その2
両側は切り立った断崖、のぞき込めば足がすくむような場所ばかりな痩せ尾根を通るルートが多く、砂利質の道は滑りやすく危険に感じる場所もあります。
昔は小笠山に入って行方不明という話がよくあったようですが、こういった条件ではうなずける話です。


しかし、そういった場所にウバメガシは生えています。
ウバメガシは乾燥に強く、本来温暖な海岸沿いの岩壁など、土壌が少なく他の植物が定着出来ない場所に根を下ろしています。

ウバメガシと同じような環境で自生するヒトツバも多いです。

急な斜面で落ち葉などによる腐植土が堆積出来ず、礫質で保水力も乏しい土壌は、適応できる植物が限られます。
温暖な地域のそういった土地で極相に達する事ができる樹木はウバメガシやヤマモモなどで、繁殖力や成長速度の違いでウバメガシが優勢なのではないかと思います。
保水力の乏しい砂利質に急峻な地形がウバメガシの林を形成していたようです。
そして低山である小笠山に本来標高の高い場所に生える山地性の植物の存在の謎…
どうやら「風」と「谷」が関係しているようです。
その3へ
昔は小笠山に入って行方不明という話がよくあったようですが、こういった条件ではうなずける話です。


しかし、そういった場所にウバメガシは生えています。
ウバメガシは乾燥に強く、本来温暖な海岸沿いの岩壁など、土壌が少なく他の植物が定着出来ない場所に根を下ろしています。

ウバメガシと同じような環境で自生するヒトツバも多いです。

急な斜面で落ち葉などによる腐植土が堆積出来ず、礫質で保水力も乏しい土壌は、適応できる植物が限られます。
温暖な地域のそういった土地で極相に達する事ができる樹木はウバメガシやヤマモモなどで、繁殖力や成長速度の違いでウバメガシが優勢なのではないかと思います。
保水力の乏しい砂利質に急峻な地形がウバメガシの林を形成していたようです。
そして低山である小笠山に本来標高の高い場所に生える山地性の植物の存在の謎…
どうやら「風」と「谷」が関係しているようです。
その3へ
Posted by NATURE DESIGN 木々 at 09:00│Comments(0)